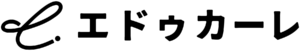あなたの日常の中に「農」を感じる瞬間は、どれくらいあるだろうか。
スーパーに並ぶ野菜を手に取ることはあっても、自分の手で育て、収穫し、食卓にのせる経験は、いつの間にか遠ざかってはいないだろうか。
実際、JA共済連が行った調査では、20代の男女1万人のうち半数を超える52.1%が「将来、農業をやってみたい」と答えている。(JA共済連、「20代の農業に関する意識と実態調査」、2024)
若い世代の多くは「農に触れたい」と思っているのに、その機会は決して十分ではない。
農業が身近でなくなった社会で、どうすれば人々と自然や食とのつながりを紡ぎ直せるのか。
その問いに向き合い、事業として形にしてきたのが、株式会社マイファーム(以下、マイファーム)の西辻一真社長だ。
今回は、西辻社長への取材を2回にわたってお届けする。前編である本記事では、マイファームがどのように多くの事業を広げ、異なる業界と手を取り合ってきたのかをたどる。
そして後編では、人や組織に着目し、顧客や従業員を仲間へと循環させる仕組みについて紹介する。
農業界のプラットフォーマーが掲げる「自産自消のできる社会」

マイファームのHPを訪れると、一番最初に「自産自消」という言葉が目に飛び込んでくる。これは西辻社長が作った造語で、「自分でつくり、自分で食べる」という意味なのだという。
マイファームは「人と農をつなぐ会社」として、農にまつわる多面的な活動を提供することで、野菜をつくる人と食べる人、そして人と自然の距離を近づけたいという思いが込められている。
現在マイファームが手がける事業は、初心者でも野菜づくりを楽しむことができる「体験農園マイファーム」や、社会人向けの週末農業学校「アグリイノベーション大学校」、さらには流通、研究開発、農業生産、企業・行政向けコンサルティングなど、農業を軸に多様な分野をつなぐ「プラットフォーム的な存在」と言われるほど多岐にわたる。
「農業ベンチャー」として創業した思いについて、西辻社長は次のように振り返る。
西辻一真社長(以下、西辻):私は幼い頃から自然に触れる機会が多く、野菜づくりと植物採集に没頭していた少年でした。でもかつては生きるための営みの一つだった「農」は、時代の移り変わりの中でしだいに生活から切り離され、人と農の距離はいまや遠く離れたものになりつつあります。 さらには、農は産業として課題が多い。それでも、農の可能性を諦めたくなかったんです。矛盾だらけの状況を嘆くより、誰もが農に関われる社会の仕組みを作ろうと考えました。

企業と農地をつなぐ、マイファームならではの役割
最初は体験農園から始まったマイファームは、近年、地方自治体や企業との協働事業にも力を入れている。
例えば地方自治体と連携し、新規就農者向けスクールの運営実績・独自カリキュラムを活かした人材育成や就農支援を行っている。また企業と連携し、マンションや施設、保育園の敷地や建物の屋上など、遊休地を活用した「どこでも農体験プロデュース」は、野菜づくりへのハードルを下げ、農業に関わる一歩目を創り出す取り組みだ。
その取り組みの一つは、「マンション併設農園」である。大手不動産会社と協業し、都市部の住宅地に農園を設け、住民が日常的に畑に触れられる環境を整えているのだ。

西辻:実は新たに農園をつくることは、そう簡単なことではありません。農地の所有者からすると、ある日突然、よく知らない企業から「農地を使わせてください」と言われても、そう簡単には信用してもらえないことも多いのです。一方弊社は、農業の会社でもあるし、JAさんとも懇意にさせていただいているので、農地・都市開発においては、不動産会社さんの力になれると思うんです。
また私たちは、今ある農地の活用方法や運営プログラム策定のノウハウもあるので、ただ「場」を作るだけではなく、その後も含めたサポートができることが強みでもあります。農業は継続が大切なのです。
こうした仕組みや場づくりが、暮らしの中で農に触れる時間を自然と生み出す。都市で暮らしながら農を体験できることで、農業と人の境界線を少しずつなくそうとしているのだ。
再エネと農業の異色コラボが導く「収益の安定化」
マイファームが取り組む事業の中で、もう一つ注目した事業がある。それが「再生可能エネルギー事業」だ。自然電力株式会社との資本業務提携を結び、ソーラーシェアリング事業を行っている。これは、農地の上に太陽光パネルを設置し、農業と発電を同時に行う仕組みだ。

西辻:最近だとメガソーラーなど、ネガティブなイメージもあるかもしれませんが、私たちのソーラーシェアリング事業は、トラクターも走れるほどパネルの間隔を広げて、太陽光が入るように設計しています。そのため、例えば野菜を育てている上で電気をつくり、その電気を野菜の加工場等で使う、ということが可能になるんです。導入前と比べて収穫量は8割程度になりますが、電力収入を加えると、農業単体よりも収益が上がる設計ができます。私たちは現在、つながりがある農家さんに協力してもらいながら、適切な光量や作物を試験しています。
エネルギーも自産自消し、自分たちの地域の中で循環させる仕組みができれば、地方は地方のままで強くなれると思うので、そんな未来を私たちは目指しています。
「収益の安定化」と「地域循環」の両立をめざすソーラーシェアリング事業は、地域に農とエネルギーの循環を生み出す挑戦として期待されている。
あえて多くの事業を展開する理由

不動産や再生可能エネルギーといった異業種との連携を通じて、マイファームは暮らしの中に農を取り戻す新しい形を提案してきた。
では、なぜあえてこれほど多様な事業に挑んできたのか。その背景には、明確な課題意識がある。
西辻:私たちは、一般的に表現される生産者を「農業者」、そして消費者を「生活者」と表現しています。これは分断をつくらずに、誰もが農に関わる未来を目指したいと思い、あえて使っています。
その「生活者」たちが自然や農業に関わる時間が減っている中で、説教をするように「農業のことを考えましょうね、食は大事ですよ」と言われても、「分かってはいるけどねぇ・・・」と感じると思うんです。だから私たちが取り組むべきことは、「自然や農業って、実は日常の中にいろんな接点があるんですよ」と提案することだと思っています。そのためには、入口を一つではなく、楽しくワクワクできる形でたくさん用意する必要があると思っているんです。
体験農園や農業学校、不動産との協業、再エネとの連携など、一見バラバラに見える各事業も、すべては「農を日常に取り戻す」という同じ思いに根ざしている。多事業展開は挑戦の数を増やすためではなく、暮らしの中に農と出会うきっかけを広げていくためのものなのだ。
次回後編では、多くの事業を展開するために工夫された組織の仕組みや、顧客さえも仲間へと循環させる企業風土について紹介したい。
写真提供・引用:株式会社マイファーム
文 :山川奈緒子
GOOD NATURE COMPANY 100 とは
「GOOD NATURE COMPANY 100」プロジェクトは、持続可能な社会の実現に向けた企業の活動内容を、おもしろく、親しみやすく、その物語をまとめたデータベースです。
風景を守る会社、生物多様性に寄与する会社……
私たちが暮らす社会には、いいことを、地道に続ける会社があります。
それを知ればきっとあなたも、こんなに素敵な会社があるんだ!と驚き、そして、好きになってしまう。
私たちは、持続可能な社会の実現に向けた企業のサスティナビリティレポートを作成し、データベース化していきます。
© Copyright EDUCERE 2024