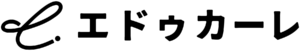便利さや「タイパ」を求めるほどに、私たちは“風”を感じる余白を失ってはいないだろうか。
今、ここ日本で「地域をつくる」とはどういうことなのか。そこに本当の豊かさはあるのか。
山梨県北杜市・清里高原に広がる複合観光施設「萌木の村」。
静かな風が通り抜けるこの地は、派手な観光地とは異なる“何か”を訪れる人にそっと手渡してくれる。それは自然のにおい、文化の温度、そして人の営みのリズムが、無理なく重なり合っているからかもしれない。
その風を50年かけて編み続けてきたのが、「萌木の村株式会社」の舩木上次社長だ。
「地域づくりは風だと思っている。風味、風景、風習、風土…その土地に吹く風を大切にしないと、風格は生まれない」と舩木社長は話す。
その言葉通り、環境省の自然共生サイトへの認定、4000トン以上の石を積み上げて作った庭、清里フィールドバレエの舞台づくり、日本一の評価を受けたウイスキーのプロデュースなど、そのどれもが、経済合理性よりも「風の質」を問い続ける実践だった。
かつて「清里ブーム」で多くの観光客に溢れたこのまちで、なぜすぐ結果に現れない庭づくりを50年も続けてきたのか。なぜ「商品」ではなく「作品」として、この場所をつくってきたのか。
その問いの先に、これからの地域と社会のヒントが見えてくる。
「昔はどこも自然共生サイトだったじゃない」

2025年春、萌木の村は環境省の「自然共生サイト」に認定された。人と自然が無理なく共に生きるこの地には、在来種を中心としたこの地に合う700種以上の植物をはじめ、豊かな生態系が今も息づいている。
対象となったのは、自然石と多年草を中心に構成された「ナチュラルガーデンズMOEGI」だ。
だが、舩木社長にとって自然共生サイトの認定は、あくまで結果だという。
舩木社長 昔はどこも自然共生サイトだったじゃない。田んぼに行けばタニシがいて、どじょうがいて、どこも共生サイトを作ろうと思ってやってたわけではないよね。
でも今は違う。風味、風景、風習、風土…その土地に吹く風を大切にしないと、風格は生まれないんだよ。そして欲望も風のうちだと、僕は思うんだよ。僕はここで、上質な欲望を田舎で提供したいんだよ。
萌木の村は今、そうした“風”の質を問う場として、静かに注目を集めている。
お金の力が地元の暮らしを飲み込んでいく、清里ブームへの「違和感」

舩木社長が東京から地元・清里に戻ったのは、大学を中退した20代の頃。息が詰まるような年功序列の村社会の中で、舩木社長を含む若者たちは、自分の思いや情熱を表現できずにいた。
舩木社長 先輩たちからは「小僧」と呼ばれ、自分たちはとにかく指示に従うだけ。当時清里には、若い人たちのエネルギーの発散場所がなかったんだ。僕もその一人だったから、まず自分のエネルギーの発散場所が欲しかったということが、今に至るきっかけだったのではないかな。
そうして開いた喫茶店「ROCK」は、やがて仲間たちの集いの場となり、「萌木の村」の始まりとなった。アメリカ文化の香りが残る開拓地・清里で育った舩木社長にとって、洋風であることや新しいことに挑むことは「水中にいる魚が水を意識しないように、僕にとっても当たり前のこと」だったと言う。
だが、80年代の清里ブームで、その「当たり前」は大きく歪んでいく。

舩木社長 雑誌などで清里が取り上げられて、たくさん人が訪れるようになったけど、町はどんどん原宿みたいになっていくわけ。田舎はもっと田舎らしくあってほしいと僕は思っていたんだよ。
急激な観光開発とメディアによる消費が進むなか、「何かがおかしい」という違和感を抱き続けた舩木社長。お金の力が地元の暮らしを飲み込んでいく光景に、焦燥と怒りを感じていた。
舩木社長 お金っていうのは、能力がないと素敵な使い方ができないと僕は思うんだよ。でも当時の清里はブームの真っ只中だったから、町の実力以上に観光客が訪れて、何となく乱開発が始まっちゃった。それは実力でも何でもないのに。
恩を返すための庭づくり
喫茶店「ROCK」誕生後、クラシックホテルの建設、オルゴール博物館の立ち上げ、森のメリーゴーラウンド設置などを経て、理想のまちを目指した「萌木の村」。2012年からは、ランドスケープデザイナーのポール・スミザー氏監修のもと、10年の歳月をかけ、敷地全体に700種超の植物が育つ「ナチュラルガーデンズMOEGI」を整備した。

舩木社長 ポールさんは、とにかく環境に優しくないことはやっちゃいけないと言うんだ。だから毎回僕は彼とケンカしてるんだよ。例えば枕木は防腐剤がついていて、虫が枕木にとまっちゃうと良くないから、枕木は使ってはダメだと怒られるんだ。僕たち素人が良いと思ってやったことが、生態系には良くないことがたくさんあるんだよな。
試行錯誤を重ね、地道に積み上げてきた歴史が、自然共生サイトへの認定にもつながった。
舩木社長 僕たちは、自分たちがやってきたことに自信を持ってなかったんだ。僕自身はある程度すごい庭ができていると思っていたんだけど、なかなか周囲にはその価値が認めてもらえなかった。でも自然共生サイトがきっかけで、地元の人にもこの庭の価値が広まってきたんだよ。

舩木社長 この前地元の大工さんたちと話していたら、「最近は多くの人が自然石に魅力を感じ、自然石を積んで、家を作るようになった」って言うわけ。僕たちには八ヶ岳の自然も含めて、宝物のような花がすぐそこにある。そういうことを、地元の人も意識し始めたような気がするな。
自然の論理に従いながら積み重ねるこの営みは、よくある景観整備ではない。それは、自分のルーツやこの土地への「恩を返す」ための営みでもあるのだと言う。
舩木社長 最近友達から届いた手紙を読んで、僕のやってる庭は、100年前、200年前の人たちに対して、恩を返すために続けているのかもしれないと思ったんだよ。だからこの庭を次の100年につないで、「恩送り」をしなきゃいけないんだ。
ROCKやホテルといった構造物はいずれ役目を終えるかもしれない。それでも、この庭は残る。それが舩木社長の確信だ。
「本物」が分かる賢い経営者でいなければならない
自然と調和する経営には、時間も手間もかかる。便利さやスピードがもてはやされる時代の中では、遠回りに映ることもある。
けれど舩木社長は、目の前の経済性ではなく、「風格」や「風の質」に価値を置いてきた。その姿勢は、時代が大きく揺れる今だからこそ、問い直されるべきものだ。
舩木社長 清里を開拓したポール・ラッシュ博士は「Do Your Best and It Must Be First Class.(最善を尽くして一流たるべし)」という言葉を残したんだ。でもその「一流」って言うのは、高額っていう意味じゃない。水がきれい、景色がきれい、人が優しい。そういう「本物」のことを言ってるんだよ。

舩木社長 それは経営でも同じ。間違った価値観の中でも、経済活動を続けられる。でも本当に切羽詰まった時には、本物しか残らないと思うんだよ。だからその本物を見極められる、賢い経営者でいなきゃいけない。
僕にはたぶん経営能力はないと思うんだよ。でも人間は基本的に役割だと思っているの。自分の役割を見つけた人が人生の勝者なんだよ。
舩木社長は、本物を残す役割を見つけたのだ。
庭づくりは、時間もお金もかかる。すぐに成果が見えない営みだ。けれど、それでもやり続けてきたのは、清里の“風”を受け継ぎ、未来へ恩を返す場所として、この場所を残し続けることに意味があると信じていたからだ。
取材の最後に、舩木社長からはこんな言葉が返ってきた。
舩木社長 大バカ者っていうタイトルにしてよ。僕は褒められるのは本当に嫌いなんだ。もう本当にありのままを書いてよ。
時代の風に背を向けながら、ただ清里の自然と人々に恩を返したい。その一心で、誰よりも手を動かし、石を積み、村をつくってきた舩木社長の姿は、その言葉通り「大バカ者」だと見ていた人もいるかもしれない。でもその姿こそが、これからの社会にとって、本当の風格をつくる希望なのだと思う。
受け継がれてこそ生きる知恵がある。歴史がある。意思がある。未来に手渡さずにはいられない。
写真提供・引用:萌木の村株式会社
取材・文 / naoko yamakawa
GOOD NATURE COMPANY 100 とは
「GOOD NATURE COMPANY 100」プロジェクトは、持続可能な社会の実現に向けた企業の活動内容を、おもしろく、親しみやすく、その物語をまとめたデータベースです。
風景を守る会社、生物多様性に寄与する会社……
私たちが暮らす社会には、いいことを、地道に続ける会社があります。
それを知ればきっとあなたも、こんなに素敵な会社があるんだ!と驚き、そして、好きになってしまう。
私たちは、持続可能な社会の実現に向けた企業のサスティナビリティレポートを作成し、データベース化していきます。
© Copyright EDUCERE 2024