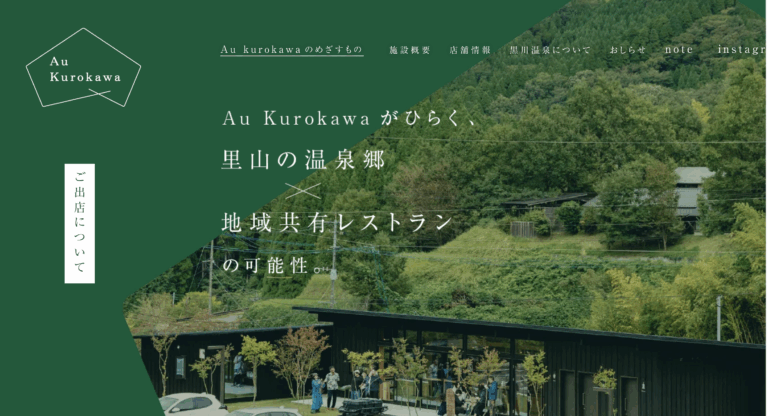あなたがテントを張るすぐそばで、絶滅危惧種のミゾゴイがヒナを育てているとしたら──そんな場所が、日本に実在することをご存じだろうか?
鳥取県八頭町にある「八東ふる里の森」は、標高750メートルの高地に位置し、近年では少なくなったブナ林に囲まれる自然豊かな町営キャンプ場だ。

近くに渓流も流れるこの森には、絶滅危惧種であるミゾゴイやコノハズク、日本でも珍しいアカショウビンなど、珍しい鳥たちが営巣する。
例年5月から7月は全国からバードウォッチャーが訪れ、園内では連日、数百万円の機材を手にした愛鳥家たちの姿が見られる。

だが、この“奇跡の森”もかつては利用者が激減し、存続の危機に瀕していた。
その森を立て直しているのが、八東ふる里の森を指定管理する「株式会社エルボスケ」だ。いま彼らは、この森をユネスコエコパークへと押し上げようとしている。
自然は守るだけでなく、生かすものでもある——その理想は本当に実現可能なのか?
その答えを探るべく、株式会社エルボスケの檀原徹典さんに話を聞いた。

「心のふるさと」を未来に残すために
檀原さんは旅行業界で長年活躍した後、2021年に母親の故郷である八頭町に移住した。幼いころ何度も通った田舎は、当時帰省を楽しみに待つほど、大好きで思い入れのある場所だ。
檀原さん 移住するちょっと前に八頭ふる里の森を訪れたんですが、当時はあまりメンテナンスがされておらず、施設も全く使われていませんでした。当然利用者も減っている状態でしたが、この森では珍しい野鳥が繁殖していて、それを目的に全国からバードウォッチャーが訪れていたんです。
キャンプ場の運営は厳しくとも、観光資源が多くはない八頭町に、全国から人が訪れる森がある。それならば、もう一度この場所を盛り上げ、未来に残したい。そんな強い思いから指定管理者としてその運営に乗り出した。

活動のポイント
1.ただのキャンプ場を「人が集まる施設」へ
運営開始後は、バンガローなどの宿泊設備や飲食の提供を整備して、利便性を高めると同時に、前職のつながりも活かしてバードウォッチングツアーの受け入れを開始。さらに愛鳥家に最新情報を提供するため、アカショウビンやコノハズクの営巣状況をホームページやYouTubeで紹介するなど、工夫を重ねた。
また、バードウォッチングのシーズンは限られるため、フィンランド政府観光局の協力を得て導入したテントサウナや、渓流を活かしたアクティビティ、星空観察など、季節を問わず魅力が伝わる体験の拡充にも力を入れてきた。

2.専門家の知恵を借りて「見せる保全」へ
野鳥や植物の希少性を伝えるには、ただ保護するだけでは足りない。
「ここには何がいるのか」「なぜ貴重なのか」「どうすれば見られるのか」。
そんな正しい知識と、伝えるための“仕掛け”があってこそ、訪れる人の“見る目”が育っていく。
そうした考えのもと、八東ふるさとの森では、自然の価値を“見せて伝える”努力を重ねてきた。その取り組みがひとつの成果を結んだのが、2025年の「自然共生サイト」認定である。
「自然共生サイト」は、環境省が生物多様性の回復を目的に、民間事業者などが行う自然保全活動を評価・登録する制度であり、認定には地域の生態系を詳細に調査・可視化する必要があった。そのため、各専門家たちに協力を仰ぎながら、地道な調査とモニタリングを積み上げてきた。
檀原さん 例えば園内の調査では、公立鳥取環境大学の小林朋道 理事長兼学長や学生の皆さんに、生きもの全般の調査や展示の企画などをお願いしています。
植物に関しては、鳥取県立博物館の清末幸久さんや、自然観察指導員鳥取連絡会の岡田祐哉さんに、植物の種類や分布など、細かく見ていただいています。

また、日本希少鳥類研究所の飯田知彦博士には、コノハズクの生態調査をお願いしていて、森の中への巣箱の設置や、営巣のモニタリングにも関わっていただいています。
アカショウビンについては、岡山理科大学の藤本義博教授に協力いただき、お客様から見える範囲でも営巣できるように、環境の整え方などについてアドバイスをいただいています。
自然と経済、そのはざまで模索する
ただ、自然と向き合う仕事には不確実性が伴う。発掘した園の宝を守りながら、どのようにして地域経済に貢献するのか。その挑戦の道のりは決して平坦ではない。
2024年には、コノハズクの営巣が約1か月も遅れたことで、当初予定していた観察ツアーがすべてキャンセルになる事態に見舞われた。自然のリズムに寄り添うこの仕事には、「予測できない」という宿命がついて回る。
また壇原さんは、気候変動や人間の手による環境整備が、生態系の微妙なバランスを変えつつあることにも懸念を抱いている。
檀原さん 住みやすい環境になると、どうしても強いものだけが残ってしまいます。専門家と連携はしていますが、最適解はやってみないとわからないんです。
実際、かつては見られなかったアオバズクが園内で営巣するようになり、より小さなコノハズクの居場所が脅かされているのだ。
檀原さん 動物園ではないので「見られない可能性」も理解していただく必要があります。不安定ですが、それを前提に事業を育てる意識が大切です。
実感しはじめた手応え、小さな循環の兆し
年々変化する自然環境に、一つずつ向き合ってきた八東ふる里の森。課題も残るが、これまでの取り組みから成果や手応えを感じる瞬間も増えてきている。
利用者を鹿や熊から守るために園の外周に張り巡らされた電柵のおかげで、結果として希少な動植物が食害から守られていたことが分かったのだ。

また先述した専門家たちとの協力も、自分たちでは気づけなかった“園の宝”の発掘にとって、大きな出来事だという。
檀原さん 当初は「花が咲いているな」くらいの認識だった植物が、専門家の目でひとつひとつ見ていただく中で、その希少性に気付かせてもらいました。園内には実は多くの希少種が息づいているので、それを大切に守りつつ、観光客の方々にも自然に触れるきっかけになれば良いなと思っています。
実際に、森の魅力を可視化する取り組みも進めており、大学と連携して展示や標本づくりも始まっている。
檀原さん 公立鳥取環境大学の授業の一環で、学生さんたちに展示や標本づくりをやってもらっています。その一つのゴールとして、森の生物多様性が一目でわかる概要図や展示を、管理棟に設置できたらと思っています。また今も地元の中高生に対して環境教育を進めていますが、これはビジネスとしてではなく、地域貢献やシビックプライドの醸成のためにも続けていきたいです。
ユネスコエコパークが示す、新しい「地域のかたち」

ここ数年、海外からのバードウォッチャーも訪れ始め、「0から1を生み出すステージ」は越えた実感があると檀原さんは言う。
檀原さんらが次に見据えているのが、「ユネスコエコパーク」への登録だ。
ユネスコエコパークは、生物多様性の保全、地域経済の持続可能な発展、環境教育の3つを柱にした国際制度。自然保護だけでなく、教育や地域産業の活性化も重視されており、人と自然が共に発展するモデル地域を目指している。
檀原さん 世界遺産は基本的に「守る」ことに重きが置かれていますが、ユネスコエコパークは「自然を守りながら人間の暮らしも豊かにすること」を目指しています。僕たちは、ただ自然を保全するだけでなく、それによって地域が元気になることを大切にしたいと思っています。
ここ数年、海外からのバードウォッチャーも訪れ始め、「0から1を生み出すステージ」は越えた実感があると檀原さんは言う。
檀原さんらが次に見据えているのが、「ユネスコエコパーク」への登録だ。

ユネスコエコパークは、生物多様性の保全、地域経済の持続可能な発展、環境教育の3つを柱にした国際制度。自然保護だけでなく、教育や地域産業の活性化も重視されており、人と自然が共に発展するモデル地域を目指している。
檀原さん 世界遺産は基本的に「守る」ことに重きが置かれていますが、ユネスコエコパークは「自然を守りながら人間の暮らしも豊かにすること」を目指しています。僕たちは、ただ自然を保全するだけでなく、それによって地域が元気になることを大切にしたいと思っています。
そのために、希少生物のモニタリングや教育活動、情報発信などを重ね、将来この森を次世代に引き継げるよう準備を進めている。

檀原さん いずれは「ここで働きたい」と思う若者が出てきてほしいんです。そのときに安心して任せられる状態にしておくのが、今の僕の役割だと思っています。
そう語る檀原さんの表情には、この地への深い愛情と責任がにじむ。
小さなキャンプ場から始まった試みが、いまや国際的な視野で動き始めている。
自然を守ることと、地域に豊かさをもたらすこと。その両立は、まだ簡単な道ではないかもしれない。けれど、いま八東ふる里の森で進められている小さな実践の積み重ねが、やがて日本、そして世界にとっての希望になる。そんな未来を、檀原さんらは静かに見据えている。